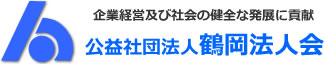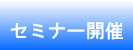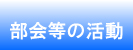2025年10月07日号
国債利率、17年ぶりに1.7%に引き上げ
財務省は10年物国債の入札で前回7~9月の表面利率を年1.5%から1.7%に引き上げた。17年ぶりの高水準となる。日銀が今後早期に利上げするとの予測から長期金利の指標である10年債の利回りを実勢金利に近づけた格好となる。表面金利は国債の買い手に支払う利子を指し、逆を言えば支払利子を上げなければ、国債は売れないということになる。ただ、金利上昇により国債費の利払い費は増えることになり、政府にとっては国債の増加が余儀なくされ、政策経費が膨らむリスクともなる。
日本の災害リスク、世界17位に引上げ
ドイツの国際援助団体「開発援助連盟」が発表した2025年版「世界リスク指数」ランキングで、日本の自然災害は前年度より7つ引上げの世界193カ国中17位となった。ランキング評価では、災害の被災度合いでは前年と変わらなかったが、災害に対する社会の脆弱性が高まったことから順位が引き上がっている。背景には、大地震や温暖化に備えて社会構造を変える長期的な戦略の評価が大きく下がったことから、社会の脆弱性が増したと指摘されている。
10月の飲食料品、3千超品目が値上げ
帝国データバンクの調査によると、10月の飲食料品値上げは3024品目に及び、今回の値上げ率平均は17%になることが分かった。前年10月と比べると、100品目多く、値上げ率も3.4%上昇し、10カ月連続で前年を上回っている。2025年通年での値上げは、12月までの公表分を含め、累計2万381品目となる見通しにある。値上げ要因では、原材料の高騰、光熱費の上昇による生産コスト増、人手不足による労務費の上昇、物流費のコスト増など複合的な要因が重なっている。
来春の花粉飛散予測、北・東日本で多く
日本気象協会が発表した「2026年春の花粉飛散予測第一報」によると、今夏の猛暑や前シーズンの飛散状況の影響から、2026年春の花粉飛散量は西日本では概ね例年並みとなるものの、北日本や東日本では例年より多いとした。前シーズン(2025年春)の花粉飛散量は西日本で例年より多かったが、翌年は雄花の形成が減少することから、来春の花粉飛散は抑えられると見ている。一方、東日本と北日本は前シーズンの飛散状況と飛散量が増加する条件が揃ったとみている。
公立病院の経常収支、過去最大の赤字
総務省が発表した自治体が経営する公立病院事業全体の2024年度の経常収支は3952億円の赤字だったことが明らかとなった。赤字となった病院の割合も83%で、過去最高だった。赤字となった要因について、物価高騰や職員給与の引き上げなどのコストアップ分が経営にとって重しとなったことが挙げられている。赤字額は前年度の約2倍近くになっており、同省の担当者は「非常に厳しい状況だ」と指摘している。公立病院の収支は、新型コロナウイルス感染拡大時に国の財政支援で黒字だったが、一転して前年度から赤字に転じている。
子どもの「2人目を望む」割合は過去最少
明治安田生命が「0~6歳」の子どもが1人いる男女を対象に「2人目を望むか」を尋ねたところ、望む人の割合は33.3%となることが分かった。前年比3ポイント減少し、調査を開始した2018年以降で最低となった。「2人目を望む」ことに躊躇する理由を尋ねると、「年齢的に不安」(49.8%)が最も多く、「将来の収入面への不安」(45.5%)、「生活費がかかる」(34.6%)が続き、年齢や金銭的要因が挙げられた。
金価格、史上初の2万円を超える
9月29日、国内の金の販売価格の代表的に指標となる田中貴金属工業の店頭小売価格が1グラム=2万18円の最高値となり、史上初めて1グラム当たり2万円を突破した。背景には、高金利だったドルの魅力が薄れ、金利は付かないものの金の需要が高まっている。同社では「中東・ウクライナなど国際情勢で不安要素が多いことも金相場を押し上げている」とみており、「有事の金」頼みの心理状態の写し絵効果を指摘している。
魅力度、北海道が17年連続で首位
民間シンクタンク「ブランド総合研究所」は2025年の都道府県魅力度ランキングで北海道が17年連続で首位となった。2位に京都府、3位に沖縄県が続き、トップ3は観光意欲で高得点となっている。調査は観光や居住への意欲など90項目について、20~70代男女からの回答を基にランキングしている。ランキングで大きく順位を上げたのは19位の熊本県で、半導体大手の台湾積体電炉製造(TSMC)が日本初の生産拠点が同県で稼働したことから、「IT・先端技術の県」のイメージから、昨年の26位から上昇している。